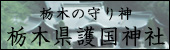「なぐさめ、なぐさめられる世界―海外戦没者慰霊巡拝―」
國學院大學研究開発推進センター専任講師(当時) 中山郁『神社新報』 平成18年 月 日 記事転載
(つづき)
その、英霊が眠る場所に行くことは、並々の苦労ではない。いまや観光が盛んなパラオやフィリピンにしても、戦跡にたどり着くには長いバスや船旅が必要である。最もきつい巡拝地のひとつとされる東部ニューギニアの例を挙げると、この広大かつ荒々しい自然に満ちた国では道路状況がかなり悪いことから、巡拝に際してトラックの荷台で十数時間以上揺られることも決して稀ではない。その上、六十数年の歳月は、陣地の跡や埋葬地を自然に帰し、現地の人々の記憶を薄れさせていることから、肉親の眠る地点自体を探し当てる可能性は極めて少ない。それでも遺族達は、一通の公報に記された戦没地名を頼りに、せめてその場所に立ちたい一心で旅路に就く。毎日四時、五時に起き、夜になるまで巡拝するのも、帰ったホテルでヤモリが這い回り、シャワーのお湯が出ないのも当たり前のことであるし、慰霊祭を行なうために入る村々は、まさしく世界ウルルン紀行そのものの世界である。しかし、旅のきつさに反比例して、巡拝中にかえって元気になる方が多い。例えば成田空港で弱々しく杖をついていた人がニューギニアに入るといつのまにか杖を手放し、そしてゆかりの戦没地が近づくと、小走りに走り出してしまう。「兵隊さんが力を与えてくれる」のであるという。ウエワク・アイタペ間の道路沿いに広がる密林には、今なお将兵の遺体がそのままの埋まって ―ないしは散乱して―いる。将兵達の「血と肉と大部分の骨とがパプアニューギニアの土地と海に融け込んでいる」(第十八軍参謀、田中兼五郎)地域に身を置き、その自然を感じることは、その地で死んだ兵隊達を感じることに他ならない。更には、怪談と切り捨てるには余りに悲しい不思議な話も、慰霊団にはつきものである。慰霊の旅に出る御遺族方にとって、御英霊が今でもその地に眠っているということは、所与の前提なのである。そうして遥々尋ね当てた場所で慰霊祭が営まれる。
各地で行なわれる慰霊祭では、祭壇に各遺族が持ち寄った故郷の水やお米、御英霊が好きであった菓子や食べ物、お酒など、故人に食べさせたいもの思い思いが山盛りに供えられ、更には在りし日の御英霊のお写真や、現在の家族の姿を写した写真をパネルにして飾る人達も多い。祭典自体は始めの黙祷以外、通常の神社祭式に則って行なわれる。その様子については冒頭に触れた通りである。祭りの場が醸し出す、惻々たる情感を伝える言葉を、私は持たない。
慰霊祭を終えた遺族達は、等しく安堵の息をつく。そこには、単に巡礼を終えた到達感だけではない何物かが見受けられる。今まで訪ねることが出来なかった済まなさを償い、土に埋められたかも定かではない肉親の「供養」を果たせたことが、心の平安を齎すのである。また、祭典場所や戦跡の石を持ち帰ることも、よくおこなわれる。西部ニューギニアのヌンホール島から石を持ち帰った遺児は「これで親父を家に迎えることが出来ました」と、しみじみ語っていた。まさしく「霊魂の復員」というべきである。慰霊巡拝とは、現地に眠る御英霊を慰めるために行なわれるが、そのことを通じて、遺族達も慰めを得るというように、生者と死者が、ともに慰めあう世界であるといえよう。
終戦から六十年が過ぎ、かって慰霊巡拝の中心を担った戦友会が主役の座を降り、遺児達も頭に白髪をたたえる時代を迎え、海外慰霊巡拝も、大きな曲がり角を迎えている。しかし、もとの戦地には、あまたの戦没者の遺体とともに、戦後、それらの方々を想って空路や海路をたどった人々の気持ちもまた、慰霊碑や学校、そして交流というかたちで込められているのである。今後は、戦没者への慰霊を介した、そうした交流の歴史を、いかに後の世代へ引き継いでゆくかが課題となろう。その存在を「忘れない」ことこそが、密林に消えていった多くの命に対する、なによりの手向けである筈であろうから。
前のページへ
参考資料室メニューに戻る